2016/06/25
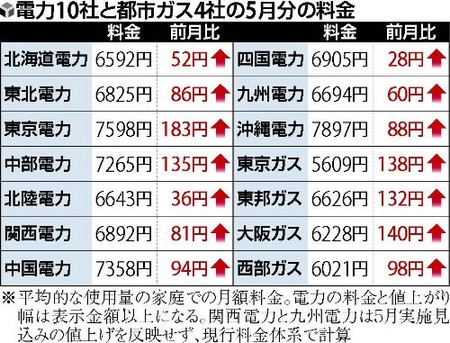
電力自由化によるデメリットと家庭生活への弊害
個人的には電力の自由化には賛成です。プランによっては料金が確実に安くなるし、競争によるサービスの向上が期待できます。
その反面、電力の自由化には潜在的なリスクやデメリットも存在します。
電気の割安料金、続々 JCOM、最大10%引き
ことし4月の電力小売り全面自由化に向けて、都市ガスや石油元売りなどが家庭向けの電気料金の公表を相次いで始めた。ケーブルテレビ(CATV)のジュピターテレコム(JCOM)は6日、大手電力より最大で10%を割り引くと発表。割安な料金で自由化の対象となる8兆円規模の市場に挑む。大手電力は近く新しい料金メニューを発表し対抗する構えで、顧客争奪戦が激化しそうだ。 (引用 共同通信)
4月からの電力自由化に向け電気売り事業への新規参入が相次ぎ、現在までに国の登録を受けた販売事業者が100を超え、自由化開始までに200程度の事業者が参入を認められる見通です。
去年暮れにはコンビニ大手の「ローソン」が参入を発表するなど、電力販売の規制緩和により電気販売業界の勢力図はとんでもないことになりそうです。
海外の事例では電力自由化で逆に電気料金は値上がりした
■電力の自由化を行っているイギリスやドイツでは電気料金が高くなっただけだった。
イギリスでは、1990年の電力自由化開始以来採用されてきた「強制プール制」がうまく機能せず、電気料金は高止まり傾向でした。ただし、逆にそのことが企業の新規参入を促し競争条件の整備につながったということもあり、新電力取引制度のNETA の導入が発表された1998年から2002年までに電気の卸売価格は40%下落し、電力自由化による成果とされています。
しかし、2004年頃からは卸売価格の上昇とともに小売価格も上昇傾向にあり、2004年と比較すると現在の電気料金は約2倍になっています。電気料金の内訳は国によって大きく異なり、イギリスの場合は発電に関わるコストの比率がおよそ3分の2程度と高くなっています。
そのため、発電に関わる燃料費の変動の影響を大きく受けます。価格上昇の理由としては、燃料として使われる比率の高い天然ガスの高騰があげられますが、他にも、利益を追求するあまりインフラなど大型の新規投資が遅れて供給能力が低下したり、二酸化炭素削減目標達成や再生可能エネルギー導入による発電コストなどのいわゆる「環境コスト」の増加も見逃せません。
こうした状況を受けて、電力自由化について様々な議論がありますが、イギリスでは、改革を進めなければさらに価格は上がってしまうという危機感があり、新たな電力市場改革を進めようとしています。日本においても、こうしたイギリスの教訓を活かし、しっかりした制度設計に基づく電力自由化を行っていくことが求められています。
引用 価格.com http://kakaku.com/energy/article/?en_article=13
ドイツでは再生可能エネルギーの普及を積極的に進めるためその全量を買取しています。日本でもその再エネ利権のコストが電気料金に転嫁され、その負担は年々増加しています。
ソフトバンクの孫社長が2011年頃まっさきに太陽光などの再生エネルギーの導入に積極的に動きましたが、当然企業の目的は『お金』『利益』です。そもそも自社の利益拡大、増加を考えない経営者なんて失格です。儲けるためなら何でもするのが普通です。
『国民の利益のため』なんて単なるポジショントーク、電力自由化で電気料金が安くなるなんて幻想にすぎません。
通信大手3キャリアも電力販売に参入
NTTdocomo、au、ソフトバンクの通信会社3社も電力事業に新規参入、携帯電話やひかり回線などのプランをセットで契約すると、料金の割引が受けられることが期待されます。
電力自由化のデメリット、2年縛り割引サービスの甘い罠
通信キャリアが参入することで懸念されるのが、電気料金の契約にも2年縛り等の通信会社の『消費者から儲けるための企業に都合のいい縛り』が出てくるのではないかと心配しています。(電力販売への解約金ビジネスの波及)
一見すると通信プランとセットの割引でお得になりそうな気がしますが、縛りのないプランでは逆に電気料金が高くなったり、2年縛りのプランを利用している家庭でも解約金せいで結局は高くつくなど・・・複雑化する料金プランで実態を分かりにくくし、料金を高く設定する通信業界のビジネスモデルが電力業界に蔓延(まんえん)する懸念があります。
事実東京電力ではTポイントやポンタなどのポイントサービスと連携してポイントを付与するそうですが、そのシステムの維持管理にかかる費用は利用者負担になります。
そんな無駄なサービスを導入する位なら直接電気料金を値引きしたほうが効率も良く、消費者にとっても分かりやすいのにいらない制度です。
電力業界の独占を防ぐための電力自由化ですが、規制緩和や新規参入で消費者の利便性や料金が安くなるなんて幻想です。
企業の本質は『儲ける』部分にあり、消費者から搾取するのが基本です。ソフトバンクのように最初は利用者のための革新的なサービスを提供したり価格競争で一時的に安くなるのですが
徐々に企業が巨大化すると保身に走り、儲け主義に走るため各社横並びのサービス、料金設定になります。
利用サービスを1社にまとめるリスク
通信プランや電力、その他のサービスの利用を一つの企業にまとめた方が割引を受けられたり、ポイントが付いたりメリットがあるでしょう。
しかし、それとは逆にサービスを一社に集中することで値上げ等でメリットがなくなったとき、他社のサービスに乗り換える時に縛られるリスクが出てきます。
当然企業の販売戦略として、その辺を計算して料金プランや縛りの設定をしてくるでしょう。
私の場合は昔に買った『テレビデオ』の購入エピソードを思い出します。
テレビデオとはテレビとビデオデッキが一体化したテレビのことで普通にテレビ+ビデオデッキを2つ購入するよりも若干安く買えます。
しかしテレビデオのデメリットはどちらか一方の機能、特にテレビ機能が壊れた場合ビデオデッキ機能が正常に使えたとしても買い替えないといけません。
それだったらテレビとビデオデッキを別々に購入したほうが、一方が故障したとしても片方を買い替えるだけで済みます。多少高くなっても分けた方がリスクとしては小さくなります。
電気料金や通信プランを1社に、しかもセットにして契約すると縛られて引っ越しやサービスを乗り換える時に違約金で返って高く付く、なんて可能性も考えられます。
『投資の基本は分散投資』
株取引やFX、国債の購入などではリスク管理のため、一つの企業に資金を全額投資するのではなく色々な分野や業種に分散投資してリスクヘッジするのが基本です。
そしてこの考え方が役に立つのは投資の分野だけではありません。
最近の電力自由化で通信業界が参入すると聞いた時に、頭の中に過った懸念が実現しないことを祈ります。





